|
お知らせ
検索窓
会社情報
でんきの話
しごとの話
個人的な話
お問合せ
最新の記事
以前の記事
最新のコメント
最新のトラックバック
私の仲間のブログ(追加順)
リンク
採用情報
|
反省しています。2006年06月30日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
本日作業中に大きな施工ミスがありました。 短時間でリカバリーできましたが、お客様にご迷惑をお掛けしたことは確かです。 大変申し訳ありませんでした。 ミスの発生原因はヒューマンエラー、いわゆる”うっかりミス”ですが、振り返ってみるとやはり事前に発生を防ぐことができたと思います。 人間誰でもミスをすることはあると思います。 しかし、ここぞという時、今回であれば「ここで施工ミスをしたら、お客様に迷惑がかかる」という局面では、やはり自己の作業の再確認が必要である、と痛感しました。 作業中の「これで良いか?」という自問自答する気持ちが足りなかったのだと思います。 また、今回は電柱で2人で作業中、そのうちの1人がミスを犯したのですが、 もう1人がその人の作業を確認すれば、ミスを発見でき、大事に至らなかったと思います。 自分の担当作業をこなすのが精一杯で、気持ちに余裕がなかったのでしょうか。 しかし、ちょっと落ち着いて「ここで施工ミスをすると大変なことになるから、相互確認しておこう。」という気持ちを持つことが必要であったと思います。 私たちの仕事では、ちょっとしたミスがお客様に迷惑をかけたり、自分たちがケガをする原因となることがあります。 今日の出来事を心に留め、明日からの仕事に生かそうと思います。
Comment(2)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?fff1eaafada8a3a2ebafb3b5a7bfaf3b 私たちの命を守る道具・低圧用手袋~その2~2006年06月28日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
 私たちが使用している低圧手袋の内側を撮影してみました。 私たちが使用している低圧手袋の内側を撮影してみました。
この製品は、ヨツギテクノ株式会社さんの製品ページによると (リンクはこちらから)、低圧二層手袋という製品になります。 確かに外側は黄色い材質でしたが、内側はピンク色の材質でできており、2層構造になっています。 この低圧二層手袋は同ページで紹介されている低圧用ゴム手袋と用途は同じです。 しかし、作業性には差があります。 低圧二層手袋の方が作業し易いです。 そのため、私たちはこちらの手袋を使用させてもらってます。 詳しい材質のことは分かりませんが、この二層になった材質が作業性の向上の要因になっているのだと思います。 私たちは他にも多くのヨツギテクノさんの製品にお世話になってます。 高圧用ゴム手袋、絶縁上衣、建築支障用防護板等ありますが、全て感電の危険性から私たちを守ってくれる製品ばかりです。 ヨツギテクノさん、いつもお世話になってます。 これからもよろしくお願いします。
Comment(2)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?818e95d0d2d7dcdd94d0cccad8c0af3a 私たちの命を守る道具・低圧用手袋~その1~2006年06月26日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
 これは、低圧用手袋です。 これは、低圧用手袋です。
私たちは、なるべくみなさんのお住まいが停電しないように工事をしています。 停電しないように工事をする、ということは電気が来ている部分に触れて作業することになります。 電気が来ている部分を充電部といいます。 充電部に触れて作業することを充電作業といいます。 この低圧手袋は低圧の充電作業時に使用します。 低圧電流を絶縁する素材でできた手袋を着用して感電を防ぐのです。 エレショックダム・モデルで説明すると、ダムの壁をより頑丈にするためにこの手袋を着用します。(エレショックダムについてはこちらをクリック) 私たちが使用している低圧用手袋はヨツギテクノ株式会社さんの製品です。 ヨツギテクノ株式会社さんでは、電気絶縁製品を多く製造しています。興味のある方は一度、ご覧下さい。 (ヨツギ株式会社さんの商品紹介ホームページはこちらから)
Comment(0)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?3939226765606b6a23677b7d6f77af39 コンセントにやって来る電気はなぜ交流?~その2~2006年06月24日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
前回のお話で、 発電所から大量の電力を効率良くみなさんのお住まいへ届けるには、 何十万Vという高電圧で送電しなければならないことをお話しました。 (詳しくはこちらをクリック) このことと交流送電にはどのような関係があるのでしょう? それは変圧の容易さにあります。 直流電流と比較すると、交流は電圧を上げたり下げたりする仕組みが容易にできる、という利点があります。 遠く離れた発電所から送電するには、超高電圧が必要 ↓ しかし、実際に家庭で電源として使用するには数百Vまで電圧を落とさなければならない ↓ そこで変圧が容易にできる交流電流が採用され、みなさんのお住まいにやって来ている訳です。 しかしながら、交流が直流よりも技術的に変圧しやすかったのは昔の話で、現在では技術も進歩し、直流電流が変圧しにくいとは言えなくなってきています。 交流送電が有利と考えられていた時代に送電設備が普及したため、現状では、交流送電が一般的となっていますが、今後の送電手段として直流送電を検討する電力会社もあります。
Comment(0)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?b1b0abeeece9e2e3aaeef2f4e6feaf38 コンセントにやって来る電気はなぜ交流?~その1~2006年06月23日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
みなさんもご存知の通り、電流には直流と交流がありますね。 お住まいのコンセントに来ている電流は交流です。 発電所で作られた電気は交流で、 発電所→送電線→変電所→配電線→柱上変圧器→みなさんのお住まい の順に送られます。 なぜ電気は交流でやって来るのでしょうか? それは、遠く離れた発電所から大量の電力を効率よく送るためです。 では、なぜ交流が遠くへ大量の電力を送るのに適しているのでしょう? それは送電する際の電圧と大きな関わりがあります。 ちょっと変な考え方をすれば、高電圧は感電しやすいですから、そんな危険な事はやめて、発電所から100Vの電気を送れば良さそうな気もします。 しかし、それは不可能です。 2つの理由があります。簡単に説明します。 1つは、距離による電力損失です。 発電所からみなさんのお宅まではかなり離れていますから、低い電圧で電力を送ると、電力の損失が著しいということです。 あんなに大きな発電所から送られてきた電力も、みなさんのお住まいに付く頃には、乾電池1本分にも満たなくなってるかもしれません。 もう一つは、送電設備の肥大化です。 1つの発電所から、100Vで送電するとしたら、そのための電線は想像できないくらい太くしなければならないでしょう。 直径10m!になるかもしれません。 そんな電線を支持できる鉄塔も想像できません。 すなわち、 発電所から大量の電力を遠くへ送電するには、 高い電圧でなければならないのです。 そのため、送電線では10万V~100万Vの電圧で電力を送電しています。 今日はここまでにします。次回に続きます。
Comment(0)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?f4f6eda8aaafa4a5eca8b4b2a0b8af3f 電柱の直径計算~応用編~足場ボルトも役に立つ2006年06月21日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
今日の話題は、ちょっと一般向きでないかもしれません。 え?これまでの話題も充分、一般向きではないですか? そうかもしれません。 でも「知っていて損なことはない。」と言いますから、本日もお付き合い願います。 また、内線電気工事業者の方には必ず役に立つ話題です。 電気工事屋さんなら、 「電柱の中間あそこ当たりの直径は何cmなんだろう?」 と知りたい時があるはずです。 地表での電柱の直径ならスケールで計れば簡単ですね。 中間ならどうしますか?直径を計りたい位置まで昇ってスケールで計りますか? おおよその寸法なら、電柱に昇らなくても分かります。 足場ボルトが教えてくれるのです。  左の写真で赤と青の丸で囲ってあるのは足場ボルトです。 左の写真で赤と青の丸で囲ってあるのは足場ボルトです。
みなさんご存知の通り、足場ボルトは等間隔で取り付けしてあります。 間隔は90cmです。 赤ボルト~赤ボルト間が90cmです。 赤ボルト~青ボルト間なら45cmとなります。 足場ボルトの数で、知りたい位置が電柱トップから何cm下にあるか分かります。 また以前お話した通り、殆んどの電柱のトップの直径が19cm、 75cm間隔で直径が1cm大きくなります。 (詳細はこちらをクリック) これらを基に電柱に昇らずとも、中間の直径を概算することが出来ます。 
左の電柱トップを撮影した写真をご覧下さい。 大半は最上部の足場ボルトがトップから約150cm下に付いています。 すなわち、 写真中の赤ボルトと青ボルトが並んでいる位置での直径は、 19cm+150÷75=21cm また、トップから2番目の赤ボルトが付いている位置での直径は、 19cm+(150+90)÷75≒22.2cm となります。 テーパー75で足場ボルトの間隔が90cmなので、 足場ボルト一本分下がったら、 直径が1cm大きくなると考えて良いと思います。 最上部の足場ボルトの位置でトップの直径プラス2cm、 その後、足場ボルト1本下がる毎にプラス1cmと考えれば、 簡単におおよその直径を見積もることが出来ます。
Comment(8)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?f7f7eda8aaafa4a5eca8b4b2a0b8af3f 電柱を建てて、まず始めにすることは・・・2006年06月19日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。

電柱を建てたら、まず最初に取り付けるもの・・・ それは足場ボルトです。 足場ボルトが付いてないと、電柱を昇ることが出来ません。   この足場ボルトは、 この足場ボルトは、
長さ約11cm、 直径約2.5cmです。 足を掛けても滑らないように、表面が凹凸状になっています。 ここで取付方法を簡単に説明します。 
電柱には足場ボルト取付け用の穴が開いていますから、 
その穴に足場ボルトのねじきり部分をねじ込んでいきます。 
最後にモンキースパナ等の工具できっちりと締め付けて、 取付完了です。 この手順で1本の電柱につき、10数~20数本の足場ボルトを取り付けます。 この足場ボルトが錆びて折れた、という話はまだ聞いたことがありません。 経験談になりますが、30年以上前に取り付けられたものでも大丈夫です。 次回は足場ボルトについて、もうちょっと突っ込んだ話をしようと思います。 そちらの方が、みなさんに役立つ情報かも・・・ お楽しみに。 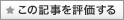
Comment(1)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?87849fdad8ddd6d79edac6c0d2caaf3e 内線施工業者の皆様へ2006年06月17日
安井電気工事会社では、以下に挙げる業務を主に行っております。
<北陸電力委託工事> 1.配電線工事 2.引込線工事 <先方工事> 1.高圧需要家受電柱の新設(建柱)・移設工事 2.高圧需要家受電柱の装柱物取付・取替え工事 3.構内柱の新設・移設とそれに伴う装柱物の取付・取替工事 (高圧・低圧とも) 4.構内架空配線の新設・取替工事(高圧・低圧とも) 5.構内柱の設備点検・碍子清掃 6.高圧充電部の建設用保護管・シート取付 主な設備 ・建柱車(4t)1台 ・高所作業車(14m、耐圧7,000V)1台 ・高所作業車(14.5m、耐圧7,000V、多関節式)1台 ・電線巻取り機(架空線用)1台
Comment(1)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?383d266361646f6e27637f796b73af3c 電柱に乗っかってる電線はどれがどれ?2006年06月16日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
みなさんのお宅の近くに立っている電柱には、色んなものが取付けてありますよね。 電線だけでもいっぱい乗っかってますよね。 一体、どれが何の電線なんでしょう? 
右の写真は、石川県白山市北安田町地内に建っている電柱です。 (写真をクリックすると拡大します。) 一番上の電線が高圧線です。 電圧は6300~6600Vです。 トランスのすぐ下にのびている電線が低圧線です。 電圧は100Vと200Vです。 北陸電力が管理している電線は、この高圧線と低圧線です。 他に電力通信線と呼ばれるものもありますが、この写真の電柱には乗っかっていません。 上から3番目(下から2番目)の線がCATV(白山市ではあさがおTV)です。 一番下の線がNTTの電話線となります。黒い長方形の箱が特徴的ですね。 最近ではNTTの線は、通常電話回線に加えて、光ファイバーの線も存在します。 この写真では、NTTの線は1回線しかありませんが、複数のNTT回線が電柱に乗っかっていることもあります。 このように複数の電線が”共架”という形で1本の電柱に乗っかってます。 電柱の所有者は北陸電力、またはNTTですが、電線の所有者は様々です。 電気屋だけが、電柱に昇るのではありません。 もしみなさんが電柱で作業している業者を見かけたら電柱のどのあたりで、どの電線に触れて作業しているか、確認してみてください。 トップで作業していれば電気屋ですが、下の方になるとそれはケーブルテレビ屋さんかもしれません。 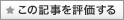
Comment(1)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?bfb2abeeece9e2e3aaeef2f4e6feaf38 土地は大切2006年06月14日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
新規に分譲された住宅地に電柱を建てることがあります。 経験談ですが、最近白山市内の住宅地では、道路ではなく、宅地内に電柱を建てることが殆んどです。 宅地内に電柱を建てれば、道路幅が電柱によって狭くならないので、交通安全面に関しては良いことだと思います。 でも、宅地内に電柱が建っていると、そこにお住まいの方にとっては喜ばしいことではありません。 ライフラインにとって電柱は必要ですが、自分の土地に電柱がどーんと建っていると邪魔ですよね。 お気持ちは分かります。 そこで、なるべく宅地内の隅に電柱を建てることとなります。 「宅地内の他敷地との境界線ギリギリに建柱すること。」 と、北陸電力より建柱位置を指示される場合があります。 そこで境界線ギリギリにアースオーガを入れ穴を掘り、電柱を建てるのですが、 結果的に電柱は境界から数cm離れた位置に建つこととなります。 何故でしょう?私たちの技術力が不足しているのでしょうか? 違います。 これも電柱のテーパーによるものなのです。 電柱の底部が地中の境界線ギリギリにあってもテーパーのせいで、地表では境界線より少し離れてしまうのです。 みなさんにとって土地はとても大切なものです。 大切な土地の中に電柱を建てさせて頂いているのですから、少しでも邪魔にならないよう、建柱しています。 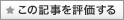
Comment(0)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?b0b1abeeece9e2e3aaeef2f4e6feaf38 レギュラーになさいますか?それともSサイズ?Mサイズ?2006年06月12日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
上のタイトル、ファーストフード店で良く聞くようなセリフですよね。 でも、これと同じことが電柱にも言えるんです。 電柱にもSとかMとかレギュラーサイズがあります。 
右の写真をご覧下さい。 電柱に埋め込んである白くて丸いものは、以前お話した電柱の規格を表示している札です(詳しくはこちらから)。 確かに「S12」と刻印されています。 「12mのSサイズ」ということです。 Mサイズは”M”と刻印されています。 レギュラーサイズはサイズの刻印がありません。 何が違うんでしょう。 テーパーが違うんです(テーパーについてはこちらから)。 日本海コンクリート工業株式会社さんの規格では、 レギュラーサイズのテーパーは1/75ですが、 Sサイズだと1/160 Mサイズだと1/110 になります。 トップの直径がいずれも同じ19cmとすると、レギュラーサイズと比較して、S・Mサイズは、ほっそりとしています。 私たち外線業者は、S・Mサイズの電柱を総じて「低テーパー柱」と呼んでいます。 12m電柱を例にしますと、地表での直径はそれぞれ Sサイズ→19cm + 1000cm ÷ 160 ≒ 25.3cm Mサイズ→19cm + 1000cm ÷ 110 ≒ 28.1cm となります。 レギュラーサイズは地表での直径が約32.3cmですから、確かにほっそりとしてますね。 みなさんのお住まいの近くにSサイズやMサイズの電柱が建っているかもしれません。 全体的にスリムなので注意してみれば、すぐに分かります。 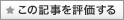
Comment(1)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?808f95d0d2d7dcdd94d0cccad8c0af3a 我が社の強みは、やはり建柱業務です。2006年06月10日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
よく会社の経営方針を検討する際に、「自社が持つ他社に無い強みを見つけ・・・」とあります。 私たちの会社の強みって言うと・・・ やはり、電柱を建てること、建柱業務ですね。 10m以上の電柱(CP)を建てるとなると、建柱車が必要です。 石川県白山市内で建柱車を所有している電気工事業者は10社に満たないと思います。 また、建柱車を操作する技術、すなわち、アースオーガで穴を掘ったり、クレーンで電柱を穴に入れる技術は一朝一夕では身に付きません。 長年の経験が必要なんです。 安井電気工事株式会社には熟練した建柱車のオペレータがいます。 私は、その社員を信頼しています。 我が社には10m以上の電柱を建てる装備と技術があることが強みです。 これだけ?いやもっとあるはずです! 後日、他の強みを報告します。 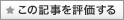
Comment(1)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?86859fdad8ddd6d79edac6c0d2caaf3e お住まいのそばにある電柱は高さ何m?2006年06月08日
北陸電力管内の配電線用電柱は全て同じ長さ(高さ)ではありません。
用途によって長さの違うものが使われています。 全長12m、14m、16mのものが良く使われています。 ここで、みなさんに質問です。 「お住まいのそばにある電柱は高さ何mですか?」 「そんなこと、知らないよ。」 ほとんどの方がそうお答えになるでしょう。でも、本当は誰にでも分かるのです。 電柱に長さが書いてあります。 では、外へ出たつもりで下の写真をご覧下さい。 
いつも何気なく見ている、いや存在すらあまり気にしない電柱ですが、近づいてみると・・・ 
高さ約2mの位置に、何やら白くて丸いものが付いています。 直径約5cmほどのものです。 もっと近づいて見てみると・・・ 
文字が刻印されています。 刻印文字の説明を上からしますと、 2006→「製造年」 14→「全長」 5.0→「強度」 1.3t→「重量」 日本海→「製造メーカー」 です。 この電柱は全長14mということです。 「そんなことを知って、何の役に立つの?」とは言わずに、みなさんも一度、お住まいのそばの電柱を見てみてください。 案外、長さよりも製造年に驚いたりします。 「こいつ、自分よりトシ食ってるよ~。」とか、「あ、子供と同じ誕生年だ。」とか・・・ あ・・・電柱を見ながら、こんなことを思っているのは私だけかもしれません。 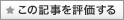
Comment(2)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?808298dddfdad1d099ddc1c7d5cdaf3d 電柱はベルボトム?2006年06月07日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
ご存知の方も多いと思いますが、電柱は頭部と底部で直径は同じではありません。 下へ向かうに従って少しずつ、太くなっています。 テーパーになっているということですね。  ジーンズに例えるなら、ベルボトムになっているんです。 ジーンズに例えるなら、ベルボトムになっているんです。
ストレートじゃないんです。 でも私、ジーンズはストレート派です。 ベルボトムは試着まではしたことあるのですが、 やはりちょっと抵抗があります。 年齢のせいですかね・・・ 本題に戻ります。 電柱は、どの程度ベルボトムなのでしょうか? 北陸電力の配電線用電柱を生産している日本海コンクリート工業株式会社さんの資料を拝見させて頂きました。 その資料には電柱のサイズによって、「テーパ1/75」とか「テーパ1/110」とか記されています。 「テーパ1/75」とは、電柱トップから下に行くにつれて、75cm毎に直径が1cm大きくなる、ということです。 一般的な電柱のトップの直径は19cmです。 また、殆どの電柱が「テーパ1/75」です。 これを基に、全長12mの電柱の地表での直径を計算してみようと思います。 12mの電柱は地中に2m埋まってますから、地上高は10mです。(詳細はこちらをクリック) ということは、地表での直径を計算すると (トップの直径)+(トップからの距離)÷75 ↓ 19cm + 1000cm ÷ 75 ≒ 32.3cm となります。 また、電柱の底部の直径は、 19 + 1200 ÷ 75 = 35cm となります。 この計算式は、電気屋さん以外の人達にも意外と役に立つかも知れません。 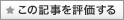
Comment(0)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?585f450002070c0d44001c1a0810af32 トランスが無いのに電気が来てる?2006年06月05日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
「あれ、うちの近くの電柱にはトランスなんて無いよ。」 と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 みなさんのお宅にいちばん近い電柱から建物に向かって電気の引込線が来ているはずです。 ですから、近くの電柱にトランスが無いと、 「トランスが無いのにどうやって電気が来てるの?」と感じる方もいらっしゃると思います。 トランスが無い電柱には、トランスが取付けてある電柱から低圧線で電気が供給されています。 
右の写真をご覧下さい。 トランスのすぐ下に縦に3本、水平方向に延びている電線があります。 これが低圧線です。 
別の角度から撮影してみました。 この写真では分かりづらいですが、トランスの低圧出力側から出ている線が、低圧線の一部と接続されています。 低圧線をトランスの無い電柱まで延長することで、トランスの無い電柱からも電気をみなさんのお宅へ供給することが可能となります。 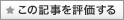
Comment(0)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?393c266361646f6e27637f796b73af3c あれ?トランスが1つだったり、2つだったり?2006年06月03日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。


右写真中の電柱にはトランスが2台、取り付けてあります。→ ←左写真の電柱だと1台しかトランスがありません。 何故、電柱によって取り付けてあるトランスが1台だったり、2台だったりするのでしょう? トランスが2台取り付けてある電柱は、その電気の供給先に動力(3相200V)を必要としている電気機器があるからです。 ”動力”とは簡単に言うと、200V、200V、200Vと3本の200Vの電気を送る方式のことです。 この方式は、モーター等に使用されます。 動力を必要とする機器の例を挙げますと、業務用冷蔵庫、業務用エアコン、水道用ポンプなどがあります。 一般住宅では基本的に動力の電気は必要ありません。 動力供給の必要が無い電柱にはトランスを1台だけ取り付ければよいわけです。 このような理由で、電柱によって取り付けてあるトランスの数に違いが生じることとなります。 ちなみに3台以上取り付けることはありません。 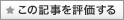
Comment(0)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?c4c0da9f9d989392db9f8385978faf33 毎日が地域の人とのふれあい?2006年06月02日
こんにちは。安井電気工事の安井健一です。
今日、高所作業車で道路を走行中、また一般車両に追い越されてしまいました。 (詳しくははこちらをクリック) みなさん、安全運転でお願いします。 今日、ある現場で作業の関係上、私有地内に高所作業車を駐車して作業しなければならなくなりました。 その場所に高所作業車をセットしないと作業不可能な状況だったのです。 所有者(一般住宅前の駐車場です。)の方に事情を説明し、高所作業車の駐車をお願いしたのですが、快諾して頂けました。 「・・・なので、申し訳ありませんが、お住まいの敷地内に車をとめさせて下さい。」とお願いすると、 「いいですよ。どうぞ。お仕事ご苦労様。」とのお言葉・・・ 理由ははっきり説明できませんが、何だかうれしかったです。 「俺たちの仕事に協力してもらえるんだ・・・」 私有地に高所作業車を駐車しなければならない時が、時々あります。 お願いした時に良い返事を頂けるよう、このブログや普段の仕事を通じて、みなさんと良い関係を築いていこうと思います。 あ、トランスの話をする約束だったのに・・・ また次回にします。 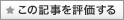
Comment(1)
Trackback(0)
この記事へのトラックバックURL
https://www.dreamblog.jp/blog/tbget.php?7472682d2f2a2120692d3137253daf31 |
